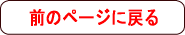| 事務局より 高校の国語の授業以来、魅かれてやまない与謝蕪村について、その足跡を作品と現地踏査の写真をまじえてお話しいただきました。舞台は大阪・京都の淀川沿川から東京・関東、さらには東北まで。内容の奥深さと面白さもさることながら、語りの名調子に惹きこまれてしまいました。音声記録でもお楽しみください。時間の都合でカットされた後半部はスライドの記録ファイルをご覧ください。本日お話しいただけなかった36歳以降の蕪村について、あらためてお聞きしたいものです。 |
| 語り手1: 和泉 守さん(1期) 「 ぶらり蕪村旅」 当初は、蕪村の生まれてから死ぬまでをやるつもりでレジュメを作成したが、そのすべてをお話しできる時間はとてもないことがわかったので、後半部分を省くことにした。 ・ 後半分を語らないということは、蕪村について何も語らないということに等しい。つまり、蕪村はまことに遅咲きの詩人であった。45・6歳で結婚し、絵画とか俳句で頭角を現したのは、50歳を越えてからである。最後の3・4年はすごくいい絵を描いている。すべてにおいて遅咲きの人であった。 ・ ということで、本日は修行時代を中心にお話しすることになる。 1. 蕪村との出会い 資料1:「春風馬堤曲(しゅんぷうばていのきょく)」(←文字をクリックすると資料1が開きます) ・ 高校時代に皆さんも読まれたことがある詩だと思う。老人が故郷に帰る途中、若い女性に出会い、一緒に話を交わしながら歩き進んだ時の詩。その女性になり代わって謳ったという題詞がついている。18の詩のうち、三番目は(原文は、漢文体)、 堤より下りて芳草を摘めば 荊(けい)と棘(きょく)と路を塞ぐ 荊棘何ぞ妬情なる 裙(くん)を裂きかつ股を傷つく 資料1の藤田真一(芭蕉、蕪村の研究家)の訳によれば、 芳しい春の草を摘もうと、堤を下りて川辺に下りて行くと、茨のとげが行く手をふさごうとする。 どんなねたみがあって、薄情にも着物の裾をいため、ふくらはぎを傷つけようとするの。 ここにある「ふくらはぎを傷つける」箇所が私はかねてより気になった。 ・ 高校の2年か、3年の国語の授業で吉永先生という、非常にくだけた授業をする先生に出会った。高校生よりも大学生や一般人を相手にしたほうがにつかわしい先生であった。この「春風馬堤曲」でも吉永先生の調子はいかんなく発揮された。 ・ 吉永先生の解釈に従えば、この箇所のこのような訳はおかしい。この詩がもつ本来のエロスの味わいが消えてしまう。参考までに、芳賀徹の訳は次のとおりである。 ふと思いついたように堤から下り匂いのいい春の若草を摘もうとする。すると刺のある木や野茨が道をふさいで邪魔をする。刺や茨ってなんてやきもちなんでしょう。ただの木のくせにさぁ。いい草の生えている所に行かせまいとして私の着物の裾を破いたわ。それに私、腿までひっかかれちゃった。おお痛い。 この訳のように、股は太もものことではないだろうか。吉永先生はこのような読み解きを授業で見事に語ってくれた。当時の純情な生徒たち、とくに私のような生徒には後々まで授業の様子が頭に残ることになった。  ・ 吉永先生は私の隣町に住んでおられた。息子も私と同じ中学・高校に行き、友人であった。先生のお宅には当時の阪神の吉田選手や御園生投手が遊びに来て泊って行ったこともあるという。先生のお宅に同居していた御親戚の方が阪神球団にお勤めであったそうである。だから、この同級生の自慢話はいつも監督の靴を磨いたとかいう話であった。 ・ もうひとり私の周りに吉田監督を知っている人がいる。中原さんという、私が勤めていた大丸の同僚である。東京の大丸商務事業部である。大丸といっても百貨店の商品とは全く関係がない。今、住んでいるマンションでも大丸に勤めていたといってもわかってもらえないので中小企業の商社に勤めていたということにしている。 ・ その中原さんがベルギーの大学を出て商務事業部に途中入社してきた。フランス人と結婚したお姉さんがパリ大丸に勤めていて、その関係で商務事業部のことを知って入社してきた。船舶課に所属し、アルジェリア向けの貨物船の輸出などを担当していた。10年間いて退社し、翻訳家として独立した。今もばりばりの現役である。もう一人の途中入社した男と三人で年一回新宿で「三人の会」と称して会っている。中途入社の多い事業部であった。中原さんは色んな本を訳している。推理小説から堅い話、核の問題まで。今回も一冊、一番軽い本を持ってきた。題名は『ぶち猫コヤバシ、とら猫タネダの禅をさがして』。この本の冒頭に 君行くや柳みどりに道長し 与謝蕪村 とあるので持ってきた。小林一茶とか正岡子規とかが出てくる。 中原さんと吉田監督との話である。 中原さんの姪、お姉さんの娘がキャロリーヌといい、パリのJETROに勤めている。キャロリーヌ夫妻が10年ほど前に来日し、1週間ほど滞在した。帰国前日になって夫のニコラがムッシュ吉田に電話したいと言い出した。なぜかと聞くと、吉田監督にパリで野球を習ったことがあり、父もフランス野球連盟の役員で監督をやったことがあるという。そんな関係で吉田監督と親しかったので電話したくなったようである。もう時間がないので、監督あてに手紙を認め、中原さんが日本語に直して送ったそうである。1週間ほどたってから監督から電話がかかってきた。こんな話を先ほどの「三人の会」で中原さんから聞いたので、私はOB1期の浦田さん(パリ在住)と吉田監督のことについて話した。その後、中原さんと吉田監督は、自著を交換したりして交流を親しく続けている。彼に言わせれば、監督はざっくばらんな人であるが、社会人としても極めて常識人。あの口うるさいフランス人から尊敬を集めたのも監督の人柄すればむべなるかなということだそうである。 ・ 萩原朔太郎『郷愁の詩人 与謝蕪村』(新潮文庫)を買ったのは、昭和35年9月、旭屋においてである。大学3年の時である。朔太郎は、群馬県出身の大正・昭和期の詩人。大正6年、詩集「月に吠える」を出している。忘れられていた蕪村を発掘したのが正岡子規とすれば、世に知らしめたのが朔太郎。この本である。朔太郎は、冒頭からこのように書いている。タイトルは「蕪村の俳句について」。 君あしたに去(さり)ぬゆふべのこゝろ千ゝ(ちぢ)に 何ぞはるかなる 君をおもふて岡のべに行(ゆき)つ遊ぶ をかのべ何ぞかくかなしき この詩の作者の名を隠して明治年代の若い新体詩人の作だといっても人は決して怪しまないだろう。しかもこれが百数十年も昔、江戸時代の俳人与謝蕪村によって詩作された新詩体の一節であることは、今日僕らにとって非常な興味を感じさせる。 ・ 朔太郎が引用したのは最初の4行だけであるが、その全詩は資料2:「君あしたに去ぬ」(←文字をクリックすると資料2が開きます)を参照いただきたい。(朗読) これが江戸時代中期の詩である。朔太郎のいうように、これを明治の新体詩といってもなんらおかしくない。蕪村は、このようなみずみずしさをもっていたわけである。 ・ はじめにあげた「春風馬堤曲」と萩原朔太郎『郷愁の詩人 与謝蕪村』が私が蕪村を好きになった出発点である。  2. スライド上映  ・ この人物が蕪村。描いたのは月渓。蕪村の弟子であるが、本職は画家。蕪村も職業画家、趣味俳句という感じがあるから、月渓も蕪村と同じ。  ・ これは蕪村の自画像。場所は、毛馬の桜宮寄りにある蕪村公園。  ・ これが先ほど紹介した「春風馬堤曲」。これは自筆であったと思う。  ・ 萩原朔太郎『郷愁の詩人 与謝蕪村』 ・ これも蕪村の画像であるが、作者は知らない。  ・ 蕪村自身は出生地について話を残していないので、どこで生まれたのかわからない。上の3つの説がある。出生年は8代将軍吉宗の時代、享保元年(1716)。  ・ 毛馬の堤にある生誕碑。「春風や堤長うして家遠し」 ・ 蕪村は出生について何も語っていない。62歳の時に、「春風馬堤曲」を作詩した折に、伏見の女弟子あてに手紙を出している。「馬堤は毛馬堤なり。すなわち、余が古園也。余、幼童の時、春色清和の日には、必ず友達とこの堤上に上りて遊び候。水には上下の舟あり。堤には往来の客あり」蕪村が育った場所について語っているのはこの手紙だけである。したがって、出生地はすべて推測である。よって、蕪村が毛馬村で育ったことは確かである。おそらく毛馬で生まれたのであろうというのが、現在の定説である。  ・ 江戸時代後期に書かれた『淀川両岸一覧』という名所案内記。 ・ 淀川の伏見から京橋、八軒家まで、宿のことを書いている。  右が毛馬、左が赤川。二つはほぼ同じ場所。赤川は毛馬より少し京都より。 ・ 帆をかけているのが三十石舟。二十八人乗り。長さ17・8m。大坂と伏見の間を、上りは12時間、下りは6時間。 ・ 蕪村の時代もこんな風景であっただろう。  源八の渡は、毛馬から大川を下ると都島橋、源八橋となるが、その源八橋にあった。  ・ 右の写真が源八橋であったと思う。 ・ 左の写真は中州から撮っている。源八の渡はこの中州あたりを往来していたのだろう。  ・源八の渡から下流に桜ノ宮。当時から桜で有名であった。  ・八軒家。建物も多く、人が行き交う。  ・ 川は恵みをもたらすが、洪水も引き起こす。淀川の歴史もその繰り返しであった。為政者は治水に力を注ぐ。仁徳天皇は茨田(まんた)の堤を造った。    ・ 伝・茨田の堤跡。京阪の大和田駅近くにある。 ・ 通りがかりの高校生3名ほどに聞いても所在を知らなかった。中年の婦人が教えてくれた。 ・ 私は、京阪沿線の千林にずっといた。ダイエーの元、主婦の店のあった所である。 ・ そのため、京阪沿線や淀川には何となく親しみがある。だから、蕪村が好きになったのかもしれない。  ・ 淀川左岸にあった文禄堤に対し、右岸にあったのが西国街道。   ・ 大和田駅から3つ、4つ大阪寄りの守口市駅から見る。橋のかかった切り通しが文禄堤。  ・橋の下に「京街道」の案内。この上(文禄堤)が京街道の起点。    ・非常によく整備されている。   ・ 京阪守口市駅。先ほどの橋の上から。     ・「右なら/のざきみち」   ・ 堤から下りる脇道  ・ 「来迎町」名前が気に入った。  ・由緒あるお寺。寺名忘却。   ・ 道標が残る。  ・ 傘と丁ちん。このようなたたずまいの店はもうあまり残っていない。  ・ 一里塚の跡。前の石は説明碑。後ろの木が一里塚。一里塚にはふつう、エノキが植えられると聞くが、これはそうではないようである。  ・ 京阪(上の黒い線)と地下鉄谷町線(真ん中の赤い線)に挟まれた赤い道が京街道  ・ 大阪に向かうときは大坂街道、京都に向かうときは京街道とよばれた。  ・ 東海道の終端部。京都からの四宿を加えて東海道五十七次が正式の東海道。 ・ 現在も国道1号は日本橋から梅田新道まで。  ・ 伊加賀は枚方市。枚方には関所があった。帆がないのは客舟。検問が終ったところで、苫をはずしたままなのであろうとの解説がある。 ・ 明治18年の大洪水(後述)は、このあたり(三矢みつや)で決壊した。  ・ 豊後橋は今の観月橋。   ・ 伏見近辺の今の地図。 ・ 伏見港公園あたりがかつての伏見港。近くに舟宿の集まる京橋があり、龍馬が間一髪難を逃れた寺田屋もここにある。 蕪村の見た淀川(資料3)(←クリックすると資料がご覧になれます) 朧月大河をのぼる御船(みふね)かな 空には朧月が淡い光を放っている。大河には貴人の乗った舟がゆったりと遡っていく。王朝絵巻を連想させる夢幻の世界、との解釈(以下を含め、藤田真一)。 みじか夜や伏見のとぼそ淀の窓 これは下り船。未明に下る。「とぼそ」は、回転させて開け閉めする扉や戸。 常は暗い中を過ぎる伏見・淀だが、みじか夜が明けそめ、伏見では戸を開け始め、淀まで来ると窓を開け放っている。 五月雨や美豆の寝覚めの小家がち 「さみだれ」は梅雨。「美豆」は宇治川と木津川の合流点。水郷地。水にかけている。 さみだれが降り続き増水した美豆では、おちおち寝ておれない小家住まいが目に付く。 居(すわ)りたる舟を上がればすみれ哉 浅瀬のために動かなくなった舟から上がると、岸辺には菫の花が咲いて待っていてくれた。夜舟に乗っての翌朝の光景か。 蕪村は何度か淀川を上り下りしている。大坂の句会への出席とか、弟子の見舞いとか。しかし、一度も毛馬に寄った形跡がない。故郷であれば途中で下りてもよさそうなものなのに、それをしていない。これにはよほど毛馬に寄れない事情があったのであろう。あるいは寄りたくない事情があったからであろう。何人もの人がこの謎にいどんでいる。 蕪村は名主の家の出であるらしいが、財産をなくして寄れなくなったとか、取り沙汰されているがすべて推測である。   ・ 左図の水色の部分、上町台地をのぞく大阪市の大部分が浸水した。市内の橋の1/4が流された。桜ノ宮の桜も大半が枯死、荒廃した。浸水15,200町歩、家屋流出1,600戸、被災人口27万人。市内交通は全域で寸断。市民生活は困難を極める。 ・ このようにして、明治18年の淀川大洪水は、河川法制定のきっかけとなり、現在の淀川堤防の基本が造られた。    ・ 放水路として新淀川(今の淀川)を開削。旧淀川は大川に。毛馬閘門で分岐する。 ・ 関東の荒川も元は放水路である。東京で大川といえば、隅田川の一部地域での俗称。大阪の大川は正式名称。     ・ この商店街は、旧毛馬村の地にはなく、道路(城北公園通り)を一つ隔てた所にある。  ・ 近所の大阪工業大学の学生が描く蕪村にちなむシャッター絵。  ・ シャッター絵の元絵。蕪村が扇面に俳句とともに描く。俳画とでも呼ぶか、蕪村の得意とするところ。  ・ もう一つのシャッター絵。冒頭でご紹介したものが下絵となっている。   ・ 電柱にも蕪村の句が。 ・ 夏の夜は短い。もう二尺も水位がさがっているこれで渡れるぞ、という意味。私は、この大井川は遠江のではなくて、京都の桂川(大堰川)ととりたい気がしている。  ・ 蕪村は二十歳(十七歳とも)の頃、江戸に出てきた。 ・ 道路「原」標は、道路「元」標が正字。  ・ 高架道路下の銘板は、徳川慶喜が揮毫。    ・ 日本橋の北側にある「元標の広場」。左の元標はレプリカ。横に市電に使われた電柱。   ・ 日本橋から北、神田方面を見る。左が三越。  ・ 先の所から100mほど歩くとこんな風情のある老舗がある。  ・ この道を50mほど入った所にある芭蕉の句碑。句は次のスライド。  ・ 蕪村は芭蕉の何十年か後に江戸に来るが、蕪村が住んだのは、先ほどの日本橋から神田に向かう道をさらに北に行った所。  ・ 師匠の宋阿(早野巴人、栃木の人)が京都から江戸に戻り、鐘撞新道に「夜半亭」を構える。蕪村はそこに転がり込む。   ・ 江戸通りの裏道を入った所にある。      ・ 1716年生まれの蕪村が夜半亭で聞いたのはおそらくこの鐘の音。 ・ 当時の時を告げる鐘は2時間おきに鳴る。12時(夜中も昼間も)に九つなり、ひとつずつ減っていく。午前4時であれば7つ。「お江戸日本橋、七つ立ち」というのは午前4時に出発する意。その次が「明け六つ」。 ・ 江戸では打つ前に、3回「捨て鐘」を打った。大坂は1回。無駄なことはしないという上方気質か。 ・ 蕪村は師匠・宋阿と40歳ほどの年齢差。弟子として非常にかわいがられた。  ・ 十思公園の近くが、地下鉄日比谷線の小伝馬町駅。そこから歩いて5・6分の所が私のかつてのオフィス。東京に出てきて5度目の引っ越し先。店(百貨店)にオフィスがあったことは一度もない。皇居の周りを転々としていた。 ・ 大門は元吉原の大門にちなむ。(元)吉原は明暦の大火で焼失移転。   ・ 当時の川柳。このあたりに江戸時代、大丸が開業していた。  ・ 江戸に来る前の暮らしは一切不明。一説に増上寺にいたという人もいる。  ・ 蕪村はたびたび号を変える。 ・ 最後の句の東武宰「町」は東武宰「鳥」が正字。 ・ この句には、師匠が孤独な自分を拾い助けてくれた、との意の前書きがある。「わが師をなくした悲しみの涙は使い古した陳腐なたとえだけれど、泉の如くいつでも湧き出てやまない」という意味である。  ・ 蕪村は師匠がなくなり、生活基盤を失う。師匠の句集を編もうとしたが、それもできず、その秋に同門の結城の砂岡雁宕(いさおかがんとう)を訪ねる。 ・ 師匠・宋阿を江戸に戻るように勧めたのは、この砂岡雁宕。 ・ 結城に10年間滞在。特定の家に居たというわけではなく、雁宕の家や寺や、下館のほうに行ったりと、あちこちを転々としていた。    ・ 結城に着いた年か翌年には東北を行脚している。正確なルートはわかっていない。 ・ 蕪村は芭蕉を敬慕するところ大きかった。 ・ 結城時代の蕪村は絵(初期の絵)はかなり残しているが、句作は少ない。  ・ 第一句は、遊行柳(白河の関)が題材。西行が訪れ、それを慕って芭蕉が訪れ、さらに蕪村が訪れた。蕪村自身もかなり気に入った句。 ・ 第二句の「うつせ貝」は中味の入っていない貝。松島の月をぼけーっと観ている人を詠む。 ・ 平泉についての句はない。  ・ 蕪村編集の最初の俳書『歳旦帳』。一門が正月に出す句集。砂岡雁宕の親戚が出版に協力している。 ・ この時はじめて「蕪村」の号を使う。  ・ 「蕪村」の号の由来の定説。「田園将(まさ)ニ蕪(か)レナントス胡(なん)ゾ帰ラザル」陶淵明『帰去来ノ辞』。「荒れた村」という意味。   ・ 蕪村は、45歳年上の早見晋我にかわいがられる。        ・ 弘経寺に伝わる、僧に化けた狸の話にちなむ。「晩秋の肌寒さのなか、僧に化けた狸が自分の毛で作った筆を噛みながら木の葉のお経を書き写している」という意。 ・ 蕪村は狸をはじめ、妖怪を好む。妖怪図鑑のようなものを書いている。    「秋のくれ仏に化る狸かな」 「きつね火や五助新田の麦の雨」 「猿どのの夜寒訪ゆく兎かな」    ・ 36歳で結城滞在を打ち切り、京都に上る。 本日はここまで。 |
  |