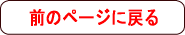事務局より
田中さんには、生い立ちから、学生時代、会社経営時代、地域社会への貢献、海外寸評、そして現在のお取り組みまで、広範囲に半生を赤裸々に語っていただきました。お話は10部構成になっています。そのタイトルを列記しますと、下記のとおりです。
1. 会社の解散を決める、平成14年3月
2. WV創部の頃、昭和34年
3. 卒業、就職そして事業継続
4. 業界(自転車)の伸張、海外を遊覧
5. 地域社会と共に
6. 大学受験に苦戦す
7. 台湾、日本人が最も親愛の情を抱く隣人
8. 欧米諸国、日本人が憧れた国々
9. 中国、21世紀の恐るべき巨大国家
10. 第4コーナーを廻ってホームストレッチへ
OB会ホームページでは、このうちのWV創部の頃について、お話の概要を以下に紹介させていただきます。
ホームページでは、お話の一部しかご紹介いたしませんが、全体の概要記録、あるいは音声記録(93MB)を
ご希望のOB会員がおられましたら、OB会事務局までご連絡ください。
田中健次さん(1期)
「旅人の足あと」
2.WV創部の頃、昭和34年
- 昭和33年の晩秋の頃であったと思う。当時フランス語科の1年生であった加納君や私が5〜6人の仲間と語らって、夕刻に大学を出発。近鉄瓢箪山駅で降りて生駒山の暗がり峠を目指す。峠の鞍部に着いた時は日もとっぷり暮れて星がきれいに瞬いていた。
- キャンプファイアこそできなかったが、峠で見た星空がみごとに美しかった。誰が言うともなく「こんなふうに野山を歩くサークルを創らんか」という話が持ち上がった。これがWV部創部のきっかけである。
- 「最近、近隣のいくつかの大学でワンダーフォゲルという活動が起こっている。あれがいいぜ。わしが資料を集めてくる」と言って、加納君が得意の情報網と人脈を駆使していろんな資料を集めてきた。
- いくつかの大学の部規約などいずれも貴重な資料であったが、そのまま借用したのでは猿真似になるので、よくわからないままに部則をつくった。
- そののち部誌『ヴィアトール1号』(誌名はラテン語からの小川君による命名)に、「外大ワンダーフォゲルは、なにを目指すべきか」という小論めいたものを載せた。そのなかで私が力説したかったことは、ワンゲル活動に文化的要素を取り入れるべきだということである。
- 当時、すでに発足していた各大学のWV部は、とくに私学のそれは山岳部的傾向が強かったように思う。しかし、山登りをやりたいという人であれば山岳部に入ればよいわけで、わざわざWV部を創る必要はない。山登りはするが、ロッククライミングはしません、といえば山岳部のジュニア版か亜流山岳部のようにみなされても仕方ないと思った。
- ワンゲル活動の基本的理念として提唱したかったことは、
- 不屈の精神: 忍耐強く最後までがんばり抜く。
- 相互扶助の精神 互いに助け合い、グループとしての集団力の向上を図る。
- 批判の精神 人のやっていることにイチャモンを付けるということではなく、自ら主体性をもって物事を判断する能力を身に付ける。
- そして、文化的要素の実践であった。
- 初年度は、夏合宿を紀伊半島と伊豆半島でワンデルング。翌年は北海道に遠征した。
- 部歌の作詞、作曲をやった。場所は風呂場である。オタマジャクシは書けないので、編曲は仙野君がやった。一番は夕暮れ時、二番は夜のキャンプファイア、三番は朝の海原、四番は山の頂上を目指して登っているところを情景としている。今でも現役の皆さんが歌っていると聞いてうれしく思う。
- 大学の校歌を作りたかった。外大に校歌はあるにはあるが、これが校歌か、と耳にするたびにいつも不満であった。母校は阪大に統合されるが、外大の校歌、大きな声で歌えるような校歌を後世に残せたら、と今でも思う。